更新日:2015/01/06(下記スペルを訂正しました)
(Thunber → Thunberg, S.avatier → Savatier, Hooke → Hooker)
日本産植物の学名: 代表的命名者たち
| 写真 | 名前と関係国 | 概略 | |
| 1 | 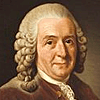 |
Carl von Linné リンネ(1707-1778)  左画像: |
命名者の省略表記は「L.」。学名の二名法を完成した。「植物分類学の祖」といわれる。世界各地から集められた標本をもとに、日本にも産する植物に多くの学名をつけた。リンネ生誕300年で、ウプサラを訪問された天皇陛下が発表された御歌(2007):「二名法 作りしリンネしのびつつ スウェーデンの君 とここに来たりつ」 |
| 2 | 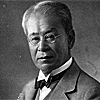 |
牧野富太郎(1862-1957) 左画像: |
命名者の表記は「Makino」: 日本の植物分類学・その知識の普及に偉大な貢献を果たし、東京都名誉都民(1953)、文化勲章を受賞した(1957)。 日本全国の植物を精力的に採集して、日本人植物学者で最も多くの日本産植物種の学名に名を残した。 |
| 3 | 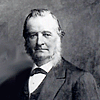 |
C.J.Maximowicz マキシモヴィッチ (1827-1891)  左画像: |
命名者の省略表記は「Maxim.」。 1860 - 1864、日本に滞在。 東アジアにおける日本植物の地理的関係を研究した。「東亜植物の父」といわれ、明治期、日本人植物学者が氏に同定を依頼した標本がロシアのコマロフ植物学研究所に今も残されているという。 命名した属の中にはイイギリ属などもある。 |
| 4 | 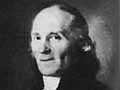 |
Carl Peter Thunberg (1743-1828)ツンベルク  左画像: |
命名者の省略表記は「Thunb.」。 長崎県出島のオランダ商館に医師として(1775)1年間滞在。リンネの高弟で、後継者として後にウプサラ大教授。日本植物学の基礎を構築したスウェーデンの植物学者、1784年には「日本植物誌(Flora Japonica)」を出版。「日本の植物を集大成した最初の著作でもある」(大場秀章)。 |
| 5 |  |
中井猛之進(1882-1952) 左画像:©「小石川植物園300年の歩み」 |
命名者の表記は「Nakai」:東京大学教授、小石川植物園園長(4代)、戦時中、インドネシアのボゴール植物園園長、国立科学博物館館長。 ケンペル、ツュンベルク、フランシェらの研究標本を現地で接し、研究した。『大日本樹木誌』1927、小泉源一と共著。 |
| 6 |  |
Adrien René Franchet (1834-1900)フランシェ  左画像:画像: |
命名者の省略表記は「Franch.」。 東アジア産植物の分類学的研究を進めた。 フランスの植物学者。 サバティエと共著で『日本植物目録』を発表した。 和名、フラサバソウは、フランシェ+サバティエに由来。 |
 |
P.A.L.Savatier (1830~1891) サバティエ  |
命名者の省略表記は「Sav.」。 横須賀造船所の医師、1866-1871に滞在し、採集した植物をフランシェへ送った。 フランスの植物学者フランシェと共著で『日本植物目録』を発表した。 |
|
| 7 |  シーボルト |
P. F. von Siebold (1796 -1866)   画像:シーボルト生誕200年記念 切手1996/02/16 |
命名者の表記は「Siebold」。 ドイツ人医師・博物学者。 長崎県出島にあったオランダ商館の医師として滞在。帰国後、ツッカリーニと共著で『日本植物誌』第一巻(1835-1844)を出版。シーボルトの意志を引き継いだ第二巻は1870年、下述のミクエルによって出版された。 |
| 8 |  |
小泉源一 (1883–1953) 左画像: |
命名者の省略表記は「Koidz.」。 京都大学植物学教室を創設、のちに教授。ケンペル、ツュンベルク、フランシェらの研究標本を現地で接し、研究した。『大日本樹木誌』1927、中井猛之進と共著で発表。日本植物分類学会の創立者で、日本の植物分類学の基礎を築いた一人。 |
| 9 |  |
F.A.W.Miquel (1811-1871) ミクエル  左画像: |
命名者の省略表記は「Miq.」。 オランダ王立植物標本館館長としてシーボルトらが残した日本の植物標本などを研究し、『日本植物誌試論』を発表した。 |
| 10 |  |
倉田 悟 (1922-1979) |
命名者の表記は「Kurata」。 東京大学農学部(林学科森林植物学)教授で樹木・シダ植物の研究者。また、植物民俗学の専門家。『原色日本林業樹木図鑑』 (全5巻) 、『日本のシダ植物図鑑』など |
| 11 |  |
Carl Ludwig von Blume (1796-1862)ブルーム  左画像: |
命名者の表記は「Blume」 オランダの植物学者。 1823-1826、ボゴール植物園園長。ライデン大教授、王立植物標本館の館長を務めた。東アジアの植物研究者。 |
| 12 |  |
大井次三郎 (1905 -1977) |
命名者の表記は「Ohwi」。 京都大学で小泉源一に師事、カヤツリグサ科の研究者。国立科学博物館の研究員。1953、『日本植物誌』を刊行。 牧野富太郎と並んで、日本の植物分類学の基礎を築いた。 |
| 13 |  |
早田文蔵(1874-1934) 左画像:©「小石川植物園300年の歩み」 |
命名者の省略表記は「Hayata」。
両親の死などで苦学しながら学問を続け、東京大学で松村任三教授に師事。台湾、インドシナの植物相の研究をした。後に東京大学教授、同植物園園長(3代)を兼任。「動的分類体系」という独自の見解を提唱した。 |
| 14 |  |
北村四郎(1906 - 2002) 画像:©「小石川植物園300年の歩み」 |
命名者の省略表記は「Kitam.」。 京都大学で小泉源一に師事、キク科植物研究の第一人者とされる。後、京都大学教授。昭和天皇の植物学研究の相談役を務めた。 |
| 15 |  フッカー |
Joseph Dalton Hooker (1817- 1911)  左画像: |
命名者の省略表記は「Hook.」。イギリスの植物学者。父W.J.Hookerの後をついで、キュー植物園の園長。 南極、ニュージランど、タスマニア、インド、ヒマラヤ、シッキム地方などを調査し多くの植物標本を収集し、植物誌として発表。 ロンドン王立協会の会長を務めた。 |
| 16 |  |
田川基二(1908-1977) |
命名者表記は「Tagawa」。 京都大学理学部植物学教室で小泉源一に師事。同時期、大井次三郎、北村四郎も在籍していた。シダ植物の分類学的な研究者。後、京都大学教授。多数のアマチュア研究者を育た。 |
| 17 |  ドゥ・カンドル |
Augustin Pyrame de Candolle(1778-1841) 左画像: |
命名者の省略表記は「DC.」。 スイスの植物分類学者。1813『植物学言論』で新たな自然分類体系(生物そのものが持つ特徴に注目して分類を行う)を発表した。「植物分類学に新時代を開いた革命者と呼ぶにふさわしい」大場秀章P280『植物分類表』2009、㈱アポック社。 |
| 18 | 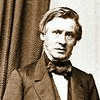 グレイ |
Asa Gray (1810-1888) 左画像: |
命名者表記は「A.Gray」。米国の植物学者。ハーバード大学教授、グレイ植物標本館設立者、米国東部植物の研究者。 1853 & 1854-55、 黒船艦隊に植物学者が乗船し、植物採集をした。その植物標本を基に、1859、植物分布に関し、アジアの極東地域と北米地域の共通性と隔離分布について世界で初めて研究発表した。 |
| 19 |  |
初島住彦(1906-) |
命名者表記は「Hatsusima」。 九州大学農学部林学科で学び、鹿児島大学林学科教授を務めた。 九州、琉球などの植物研究者。著書に 「琉球植物誌」、『琉球の植物』、『日本の樹木』、「鹿児島県植物目録」などがある。 |
| 20 |  |
原 寛(1911-1986) 左画像:©「小石川植物園300年の歩み」 |
命名者表記は「H.Hara」。 東京大学で中井猛之進に師事。ハーバード大学に留学。日本とアジア大陸、北米東部との植物相の解明に力を注いだ。東京大学教授、日本植物学会、日本植物分類学会会長を歴任、植物学の発展と国際交流に功績した。 |
番外編
 |
須川長之助(1842年-1925) 画像: |
岩手県出身。ロシアの植物学者、マキシモヴィッチ(Maxim.)の助手として植物採集をし、Maxim.が死去するまで標本を送り続けた。Maxim.が学名発表の際、献名した植物の内、★本サイト、イヌシデがある。 マキシモヴィッチとの心温まるエピソードは、★本サイト、サイカチで紹介している。氏については、『伊藤篤太郎』 岩津都希雄、八坂書房P120-123も、おもしろい。 | ||
 ウィルソン |
Ernest Henry Wilson (1876–1930)  左画像: |
命名者表記は「E.H.Wilson」。英国人プラントハンター、後に米アーノルド樹木園管理者。2度来日し、クルメツツジ、日本のサクラ、ウイルソン株と呼ばれる屋久杉を世界へ紹介した。プラントハンター時代の内容は『プラントハンター 東洋を駆ける』(アリス・M・コーツ著/遠山茂樹訳、㈱八坂書房 )がおもしろい。★本サイト、アジサイの学名で掲載。 | ||
 フォーチュン |
Robert Fortune (1812 - 1880)  左画像: |
スコットランド出身のプラントハンター・植物学者。中国からインドへチャノキを移植したことで有名。手段は今では考えられない方法だったが、現在の英国の紅茶文化の拡がりは彼の成功があったからで、もし失敗していたら、相当遅れたか、今ほどの拡がりはなかったのではないだろうか。 ★本サイト、アオキ、チャノキ、シュロで掲載。 |
||
参考図書
| 『小石川植物園300年の歩み』 | 大場秀章編集 | 1996 | 東京大学総合研究博物館 | ||
| 『植物の学名を読み解く』 | 田中 學 | 2007 | 朝日新聞社 | ||
| 『多様性の植物学』)(1)植物の世界 2.3:「日本の植物相研究と植物誌」 |
(1)構成要素の発見: 邑田 仁 |
2000 | P29、東京大学出版会 岩槻邦男・加藤雅啓 編集 |
||
 『小石川植物園300年の歩み』 |
 『植物の学名を読み解く』 |
 『多様性の植物学』 |
Copyright (c) 2010 Shizen-Aigokai Suginami(SAS). All Rights Reserved.