| チャノキ (ツバキ科ツバキ属) | |
| ツバキ科 | Theaceae |
| 学名 | Camellia sinensis (L.) Kuntze (1887) |
| 属名の意味 | 人名由来:チェコスロバキアの宣教師、Jiri Josef Kamel (1661-1706)に因む |
| 種形容語の意味 | 地名由来:「中国産の」 |
| 命名者 | |
| 和名の由来 | 漢名「茶」の音読みによる |
| 分布、生育地 |
|
| 樹形 | 常緑低木:シネンシスは茶葉用・高木はアッサムで紅茶用(アッサム起源の Camellia sinensis var. assamica があり、葉が大きい)。 |
| 葉 |
|
| 花・受粉 | |
| 果実・散布 | 蒴果で冬に熟すと3裂し、3個の果実がでてくる。重力散布・動物散布? |
| 「茶摘み」 「文部省唱歌」 作詞・作曲不詳 |
|
| 用途 | |
| 都道府県の木 | 栃木県 |
| 参考図書 | |
 花:「公園」のツバキ科では一番早く咲く。撮影: 2010・10・27 |
 葉:鋸歯は細かく、表面に光沢がある。撮影:2012/09/12 |
 果実:中の果実が大きくなると、緑色の外皮が裂ける。中に3個の果実がある。撮影・2012/10/03 果実:中の果実が大きくなると、緑色の外皮が裂ける。中に3個の果実がある。撮影・2012/10/03 |
 【畑の境界木】強い春風から赤土の畑を守るため、武蔵野台地では畑の境界にチャノキやウツギを植栽してきた。三富新田で撮影: 2010.03.27 |
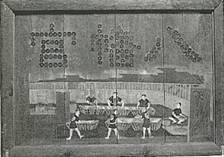 「茶作り」絵馬、菊川英山 画:明治17年(1884)。井草八幡宮所蔵、©『杉並の絵馬』絵馬は杉並区登録文化財 |
輸出品だったお茶: 明治16年には上下井草村では総戸数の二割ほどが製茶に従事。「当地域(井荻村)での茶業は、規模は大きくはなかったが、人々の生産意欲は強く、本絵馬(左画像参照)の奉納は、新しい農産物にかけた農民の心情と厚い信仰心を物語るものといえよう。」左の絵馬が登録文化財に指定されたときに提出された文章。 |
 今では垣根として利用:常緑、葉が密につく、耐強剪定で垣根向き。造園師による行き届いた垣根は気持ちがいい。杉並区で撮影:2012/07/04 |
 茶葉:撮影: 2013/01/21 |
 日本茶:発酵を防ぐために、茶葉を摘むとすぐ蒸し、熱を加え(発酵を止める)、もみ、乾かす。参考資料:朝日新聞2013/01/20の「Globe」。撮影: 2013/01/21 |
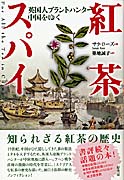 『紅茶スパイ』サラ・ローズ著、築地誠子訳、㈱原書房、2012。中国から茶の製法とタネの入手に成功した英国人★本サイトフォーチュン(左青字クリック後24番目)。 |
 茶畑(1):東京都東久留米市の村野家では茶畑が自邸内にあり、自家用の茶葉を収穫している。撮影同地で:2013/05/22 |
 茶畑(2) :左と同所。遠くに見えるのは屋敷林で、高木のケヤキ、シラカシ、スギ、竹林などがある。敷地およそ4000坪。 |