
コブシの冬芽: 撮影: ©鳥川 豊氏
| 04:植物の冬越し |
| 1.ラウンケケルの生活形 | 2. 地上 植物 |
3. 冬芽の 種類 |
4. 鱗芽の 樹木 |
5. 裸芽の 樹木 |
6. 地表 植物 |
7.半地中 植物 |
8. 番外編 |
| 1. ラウンケル (Christen Raunkiaer) の生活形 (Raunkiær's life forms) | |||
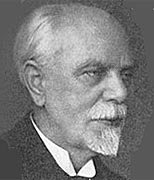 ラウンケル 植物生態学者 画像: |
|||

| 04:植物の冬越し |
| 1.ラウンケケルの生活形 | 2. 地上 植物 |
3. 冬芽の 種類 |
4. 鱗芽の 樹木 |
5. 裸芽の 樹木 |
6. 地表 植物 |
7.半地中 植物 |
8. 番外編 |
| 1. ラウンケル (Christen Raunkiaer) の生活形 (Raunkiær's life forms) | |||
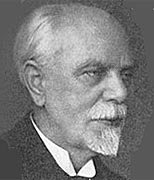 ラウンケル 植物生態学者 画像: |
|||
| 分類 | 生育不適期の休眠芽の過ごし方 | 例 | |
| 1. | 一年生植物 | 種子として地中にある | アサガオなど(説明は省く) |
| 2. | 地中植物 | 休眠芽として球根、地下茎が地中にある | 球根類など(ユリ、ヤマノイモなど)説明は省く |
| 3. | 半地中植物 | 休眠芽が地表にある | ススキ・タンポポなど |
| 4. | 地表植物 | 休眠芽が地上25(30)cm未満につく | ヤブコウジなど |
| 5. | 地上植物 | 休眠芽が地上25(30)cm以上につく | 低木~高木、 つる性植物など |
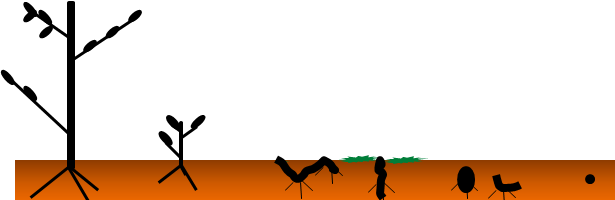 5 4 3 2 1 注: 他に水中(生)植物もあるが、ここには含まず。画像:©筆者 |
|||
| 2. 【地上植物】: 常緑樹・落葉樹・針葉樹(1の図では5番の植物) 参考資料:『朝日百科植物の世界』13-164(71号)菊沢喜八郎、13-228・229(95号)土田勝義 |
||
 常緑樹(サザンカ)借用画像:©鳥川 豊氏。冬が短く・夏が長い:冬の間の維持コストによる減少分は少ないから、古い葉を落とさずに翌年も使うという方式(常緑性)が有利。 常緑樹の葉:葉の表面にクチクラ層が発達していて、内部の凍結防止、乾燥防止の役目を果たしている。 |
 落葉樹(ユリノキ)借用画像:©鳥川 豊氏。冬が長くなる:冬の間の維持コストの減少分が大きくなるので、葉の寿命を短くし、適期に葉をつけ替える夏緑樹(落葉性)が有利。 地上植物は低温・乾燥にやや弱い。特に条件の厳しい冬、常緑樹・落葉樹の冬芽(休眠芽)は、芽鱗や裸芽で保護しながら冬ごしをする。 |
 針葉樹(クロマツ): 冬が更に長くなる:一夏で葉を替ると、コスト収支が悪化するので葉の寿命を長くする常緑針葉樹が有利。 針葉樹類の葉: 表面はクチクラ層が発達、葉の中に樹脂を蓄える組織があり、樹脂分が不凍液で凍結防止・そのワックスで乾燥防止の役目を果たしている。 |
| 3. 【地上植物の冬芽の種類】(1の図では4・5番の植物):参考資料: *『樹木の冬芽図鑑』菱山忠三郎 1997 ㈱主婦の友社・『木の芽の冬ごし』宗方俊遃 1981 ㈱岩崎書店 |
| 鱗芽 | 葉が変形した芽鱗(鱗片)で冬芽が保護されている。1枚~20枚程度の芽鱗に包まれているものなど色々ある。芽鱗は寒さや乾燥、枝同士のこすれ合いによる損傷、動物の食害などから、その中の若い葉や成長点を保護している。*P10 鱗芽をコートに見立てると、毛皮、革、重ね着など様々な工夫が見られる。 |
| 裸芽 | 芽鱗によって芽が保護されていない裸の芽のこと。芽が凍りにくいように 糖分濃度、毛などに工夫があるといわれている。暖かい地方、湿潤な環境にその起源があるのではないかと考えられている。よく比較される武蔵野台地でも見られる、ミズキ(鱗芽)・クマノミズキ(裸芽)だが、ミズキは比較的よく観察できるが、クマノミズキは少ない。 |
| 4. 【地上植物:鱗芽】(上図では4・5番の植物)休眠芽が地上につく | |||
 ニワトコ(鱗芽) 特徴は先端の枝が枯れる(die-back)現象。花と葉が混じる混芽。借用画像:©安藤 伸良氏 |
 イヌビワ(鱗芽) 右の球形は雄果のう。雌果のうは冬期にはない。借用画像:© 安藤 伸良氏 |
 ユリノキ(鱗芽) 裏革のコートのような冬芽で一対になっている。ユリノキは北米原産。 |
 ミズキ(鱗芽) 枝・冬芽とも紫紅色。冬場の枝が美しいので、ドンド焼の枝に使われるのではと思う。借用画像:© 安藤 伸良氏 |
 コブシ(鱗芽):ミンクのコートの様な銀色の軟毛に包まれている。借用画像:©鳥川 豊氏 |
 アオギリ(鱗芽):ビロード状のコートの重着の様に完全防備している。借用画像:©安藤 伸良氏 |
 トチノキ(鱗芽):硬い革コートの様な鱗芽がベタベタの樹脂でコーティングされている。借用画像:©安藤 伸良氏 |
 ヤマグワ(鱗芽) 写真は側芽で葉痕は半円形。維管束痕多数。借用画像:©安藤 伸良氏 |
| 6. 【地表植物】 (1の図では4番の植物) 休眠芽が地上25(30)cm未満に付く(NETでは、30cmというのものが多い)。林床で見かける植物。 |
||
 クサイチゴ:名前と違い、木本。図鑑では「落葉小低木」とあるが、東京では冬期に赤くなる葉も少しはあるが、ほとんどの葉は常緑状態で冬越している。撮影: 1月下旬 |
 ヤブコウジ:林床で見かける植物。常緑小低木。林床は落葉た積もり、樹木下なので乾燥・低温を避けられる。茎の上部に小さな冬芽を付ける。撮影: 1月下旬 |
 マンリョウ 林床で見かける植物。常緑小低木。撮影:1月 |
| 7. 【半地中植物】 (1の図では3番の植物)休眠芽が地表(近く)にある | ||
 カントウタンポポ:冬でも日射しのある場所でロゼット(根生葉)で冬越。撮影1月下旬 |
 ススキ-1:「半地中植物で、 冬芽の位置が地表面にある。撮影: 2015/02/11 |
 ススキ-2:地上茎は枯れているが、早春には根元に緑色が見えていた。撮影:2015/03/14 |
| 8. 【番外編】 (2015/01/12) | ||
・ 01/18に、展示会場と観察会場で、植物の冬越し全体についての解説をした。 ・ 観察会では、グループ別に、スタッフ全員が持ち回りで代表的な冬芽を解説した。 ・ 解説した冬芽:15種(裸芽:7種・鱗芽8種)の実物見本と解説用パネルは予め用意した。 ・ 選定樹木の下で各タッフが解説した(★最下段左端/中央写真)。 ・ 参加者には観察会場でも、虫めがねを使って実物見本を見てもらった(★最下段右端写真)。 ・ 参加者: 16人、スタッフ:9人、無料 (参加者保険代、資料代は会が負担) |
||
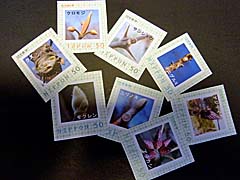 安藤伸良氏発行の冬芽の切手(1)借用画像:©安藤伸良氏・2013/12/13 |
 安藤伸良氏発行の冬芽の切手(2)フォルダー入りの切手。借用画像:©安藤伸良氏・2013/12/13 |
 準備ができた展示会場:裸芽/鱗芽には色違いのテープを巻いた。撮影:善福寺公園SC |
 展示会場での関係者たち。撮影:善福寺公園SC・2009/01/18 |
 観察会:グループ別に対象樹下で用意したパネル+実物見本で解説 |
 見本を虫めがねで見る:鱗芽の枝には種名記入の赤色テープ、 |