|
||||||||||||||||||||||||||||||
| サイカチ(マメ科サイカチ属) | ||
 安定帯(高水敷より上)/半安定帯(高水敷)/半安定帯(中水敷)/低水路:水辺のエコトーン(移行帯):水域・陸域へ移行する環境 |
水辺のエコトーン(サイカチ) 左図では、最左の安定帯より右側、半安定帯などで見られる。水辺に近いので、地下水位は比較的高い。画像:©国土交通省関東地方整備局。参考資料: 「水辺のエコトーン」:桜井善雄「水辺の自然環境」1994 |
|
 1)サイカチの棘:日本産植物でこのように鋭い棘があるのは他にないのではないだろうか?画像提供:須永三紀夫氏 |
 2)サイカチの果実:果実は、同じ枝にかたまってついていた。武蔵野市で撮影: 2012/12/08 |
 3)雄花:雄花、雌花、両性花があるとのこと。環境条件が整い、果実が結べるまで成長すると、経験では、雌花/両性花になるようだ。画像提供:須永三紀夫 |
 4)高木サイカチ:樹木の上部に果実をつけている。武蔵野市で撮影: 2012/11/29 |
 5)「公園」のサイカチ:観察会の下見で発見した。ポイントは棘。撮影: 2011/11/30 |
 6)サイカチの果実:鞘を振ると、豆が動く音がする。撮影: 2012/11/29 |
| サイカチマメゾウムシ(ハムシ科) 記:2014/12/04 | ||
 1)サイカチマメゾウムシが開けた穴:(1)安藤伸良氏が観察会下見に持参して撮影:2014/11/24 |
 2)サイカマメチゾウムシが開けた穴:左の拡大: 2014/11/24 |
 3)サイカマメチゾウムシと穴が開いた豆:撮影:同左 |
| サイカチマメゾウムシの成虫(体長約6mm) 記:2014/12/07 | ||
 4)開けられた豆とサイカチマメゾウムシの成虫。借用画像:撮影:2014/12/03・©安藤伸良氏 |
 5)豆の穴にサイカチマメゾウムシを入れて撮影。触角がないのが残念。借用画像:撮影:2014/12/04・©安藤伸良氏 |
 6)サイカチマメゾウムシの成虫:『ドルサミンA』の発見NEWSから。借用画像©広島大学太田伸二教授(大学院生物圏科学研究科)。★広島大学>研究>研究NOW>第34回太田伸二教授(画像使用許可:14/12/05)) |
| サイカチ:利用の歴史 | ||
 1):杉並区堀の内、妙法寺のサイカチは幹回りの太さが2m以上はありそう。撮影当日、お掃除をされている方に立っていただいた。ご協力に感謝。撮影:2012/08/17 |
 2)左のサイカチの上部。20mはあろうかという立派な高木。社寺林の一木として残った杉並区の宝。撮影:2012/08/17 |
 3)葉(偶数羽状複葉):数年前には、下井草湯の所有者の邸宅に本種の古木があった。しかし、撮影のために今回訪問したら、古木はなく、その古木から成長した幼木があった。区内で撮影:2010/06月 |
| 『ダニイル・須川長之助』に、マキシモヴィチ.が長之助の頭をサイカチで洗う場面 | ||
 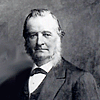 1)左:須川長之助(チョウノスキー) と右:マキシモヴィッチ(マキシモ氏)。マキシモ氏はロシアの植物学者で幕末に日本に滞在した「東亜植物の父」と呼ばれた。氏に雇われたのがチョウノスキー(愛称)で、2人の信頼関係が右掲載の本に記載されている。画像: |
 2) 「ダニイル須川長之助』(児童書) 井上幸三、©岩手植物の会、1997。右の記載文: マクシモ氏がチョウノスキーの髪を切り、サイカチで頭を洗ってあげる場面 |
|
Copyright (C) 2010 Suginami-no-Shizengaku. All Rights Reserved.