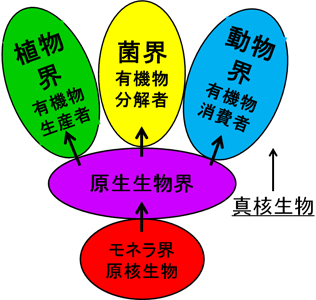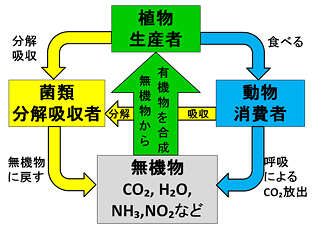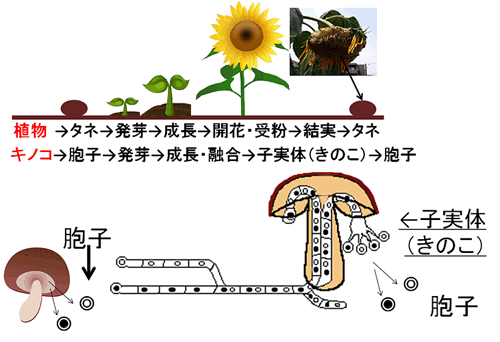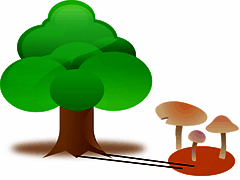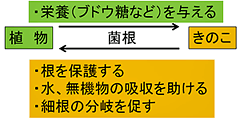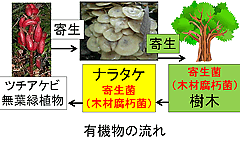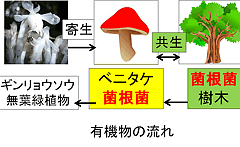| 8:木材腐朽菌:ここでは樹上性のキノコとした。(ナラタケモドキは地面から発生していたが、ここに入れた) |
 木材を腐朽(腐食による劣化)させる腐生菌のうち、特に、木材に含まれる難分解性のリグニン、セルロース、ヘミセルロースを分解する能力を持つもの。 木材を腐朽(腐食による劣化)させる腐生菌のうち、特に、木材に含まれる難分解性のリグニン、セルロース、ヘミセルロースを分解する能力を持つもの。
 褐色腐朽菌: セルロース・ヘミセルロースを分解して材は茶褐色に 褐色腐朽菌: セルロース・ヘミセルロースを分解して材は茶褐色に
 白色腐朽菌: ” ・ ” ・リグニンのすべてを分解する。材は白色になる。。 白色腐朽菌: ” ・ ” ・リグニンのすべてを分解する。材は白色になる。。 |
| |
|
|

アラゲキクラゲ:キクラゲ科:P233: (白色腐朽菌)。クワの剪定枝から発生。撮影: 2008/05/15 |

エノキタケ:左写真の裏側。「傘の表面は黄褐色で、ヌメリがある。柄はビロード質などが同定ポイント」と教わった。撮影: 2010/02/18 |

エノキタケ:キシメジ科:P55
(白色腐朽菌)。落葉樹の立木に発生。
撮影: 2010/02/18 |

イヌセンボンタケ:ヒトヨタケ科:P91: (白色腐朽菌?)。伐採木近くの地面から発生。 撮影: 2008/10/01 |

カワウソタケ:キコブタケ科: (白色腐朽菌)。 ソメイヨシノの立木に発生。撮影: 2008/07/12・鳥川 豊氏 |

カワラタケ:サルノコシカケ科: P196、(白色腐朽菌)。伐採木から発生。撮影: 2007/09/15・横川信由氏 |

イヌセンボンタケ-1: 撮影: 2016/09/26 |

イヌセンボンタケ-2: 地面に広がる。左と同地同日。 |

イヌセンボンタケ-3: 見上げると立木。左と同地同日。 |

キクラゲ:キクラゲ科:P233 (白色腐朽菌)。切株から発生していた。撮影: 2007/04/20・鳥川 豊氏 |

キクラゲ:キクラゲ科:P233。(白色腐朽菌)。伐採木から発生していた。 撮影: 2009/06/17 |

キララタケ:ヒトヨタケ科:P90: (白色腐朽菌?): 切株から発生していた。撮影: 2008/07/01・鳥川 豊氏 |

コキララタケ:ヒトヨタケ科:P90:(白色腐朽菌?)。ケヤキの伐採木に発生した。撮影: 2008/06/08・笹本英彦氏 |

クジラタケ?:サルノコシカケ科
(白色腐朽菌?)。落枝に発生。撮影: 2008/06/05・笹本英彦氏 |

オオミノコフキタケ:サルノコシカケ科(白色腐朽菌)。多くのソメイヨシノから発生している。撮影: 2008.08.31・笹本恵子氏 |

チヂレタケ:コウヤクタケ科:(白色腐朽菌)。サクラの立木から発生。撮影:2008/10/26 |

チャカイガラタケ:サルノコシカケ科:P202、(白色腐朽菌)。伐採木から発生。撮影: 2008/10/22 |

ツヤウチワタケ:サルノコシカケ科:P185、(白色腐朽菌):伐採木から発生。撮影: 2008/10/22 |

ナラタケ:キシメジ科:P42:大館一夫氏の参照本では「腐生菌/寄生菌」としている。(白色腐朽)。サクラの切株から発生。撮影:2008/10/26(観察会当時) |

不明キノコ?(ツバがない)-1:傘は直径、十数センチ程。反対側の根元に数本あったが、踏みつぶされていた。撮影:2010/06/09 |

不明キノコ?(ツバがない)-2:左写真を横から撮影した。サクラの根元から発生していた。(生活型分類もここでよいか不明)。撮影: 2010/06/09 |

ナラタケモドキ-1:キシメジ科:P43: (白色腐朽)リング状に発生しているようだ。撮影: 2010/10/06 |

ナラタケモドキ-2: 笹本恵子氏が同定した。撮影: 左同所・同日 |

ナラタケモドキ-3: 柄にツバがない。撮影: 左同所・同日 |

ナラタケモドキ:キシメジ科: (白色腐朽)地上から発生。 撮影: 2008/07/17・鳥川 豊氏 |

ナラタケモドキ:キシメジ科: (白色腐朽)地上から発生。 撮影:2007/09/24 |
ナラタケモドキ:
 撮影年月日と場所: 上段一行のみ同一日で、左2枚は別年に撮影。発生場所は、ほぼ同じ場所。 撮影年月日と場所: 上段一行のみ同一日で、左2枚は別年に撮影。発生場所は、ほぼ同じ場所。
 上段の一行は発生から日が経過していると思われる。それらに比して、左2枚は比較的に若く見える。 上段の一行は発生から日が経過していると思われる。それらに比して、左2枚は比較的に若く見える。
 特長:ナラタケはツバがあり、ナラタケモドキはツバがないとされる。 特長:ナラタケはツバがあり、ナラタケモドキはツバがないとされる。
 ナラタケ/ナラタケモドキは菌糸束を地下で形成し、地上でキノコを発生させることがあるらしい。 ナラタケ/ナラタケモドキは菌糸束を地下で形成し、地上でキノコを発生させることがあるらしい。
|

イタチタケ?:ナヨタケ科:(白色腐朽)落葉樹の根元から発生。撮影: 2008/06/05 |

ヒラフスベ:タコウキン:(多孔菌)科P189、(白色腐朽菌)クヌギの伐採木に発生。撮影: 2008.06.08・笹本英彦氏 |

マンネンタケ:マンネンタケ科P206、(白色腐朽菌)広葉樹の切株から発生。撮影: 2008.07.17・鳥川 豊氏 |

ヤナギマツタケ:オキナタケ科:P97、(白色腐朽菌)落葉樹の立木から発生。撮影: 2008/08/27 |

ヤナギマツタケ:オキナタケ科:(白色腐朽菌)落葉樹の立木から発生。 撮影: 左と同所・同日 |

不明キノコ-1:トチノキの立木の洞から発生。傘は10cm以上あた。高所で傘表を撮影できず。撮影: 2012/11/07 |