| 1:花蜜食の鳥 | 2: 鳥媒花 | 3: 鳥媒花-ウメ |
4:鳥媒花-サクラ | 5:鳥媒花-ビワ |
| 6:鳥媒花-ヤブツバキ | 7: 散布される種子 | 8:果実の分類 | 9:発芽植物 | 10:黒い果実 |
| 11:赤い果実 |
| 参考図書: 2016/04/05 |
★HP「福原のページ」福原達人氏 ★HP「鳥媒花」ウイッキペディア ★HP「サントリーの愛鳥活動」の「ヒヨドリ」と「メジロ」 ★HP「平塚市立博物館」「野鳥の観察④」 ★HP「まちのみどりと園芸の相談Q&A」千葉大学「ビワ」 ★HP:出典:環境省>自然環境局>外来生物法: 「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」(生態系被害防止外来種リスト)(「「要注意外来生物」は発展的に解消され」新しく上記を発表:平成27(2015)/03/26)。 本頁で同リストに記載されている植物種は、ビワ(178:産業管理外来種)、トウネズミモチ(53:重点対策外来種)、ピラカンサ(119:その他の総合対策外来種)。閲覧:2016/04/05。 長い名称なのでしょうか。英語の「Invasive alien speciesから「侵略的外来種」ではいけないのか知りたいところです。 |
| 1: 花蜜食の鳥:鳥が花粉を運ぶ送粉者(ポリネーター)「送粉共生係」 本ページでは身近な野鳥のヒヨドリ、メジロについて言及 |
| ヒヨドリ | メジロ | |
| ヒヨドリ科、全長28cm、重さ65g前後、留鳥/漂鳥、通年。全国の樹木の多い庭/公園/農耕地、雑木林、高原周囲の森などに生息。春/秋には集団で渡りをする。 | メジロ科: 全長12cm、重さ10g前後、留鳥/漂鳥、通年。全国の低山帯から里山の常緑/落葉混交林、樹木の多い庭/公園などに生息。 |
|
| 耳羽: 茶褐色、背~腰色:暗灰色、嘴: 黒く長い | 目の周り:白(和名の由来)、背~腰色:黄緑だが喉は黄色、嘴:細く鋭い | |
| 雑食性。木の実、花の蜜:「熱帯が主生息地であった祖先ヒヨドリの名残り」(サントリーの愛鳥活動)、花弁、軟草、昆虫類、小型両生・爬虫類 | 小型昆虫類の幼虫、クモ類。木の実、花の蜜など。「メジロもアジアの熱帯地域に生まれた鳥と考えられている」(サントリーの愛鳥活動)。 | |
 1. メジロとヒヨドリ; (大きさは画面に合わせた)。画像:©高久晴子氏 |
 2 ヒヨドリの嘴: 黄色い花粉がついている。画像:©高久晴子氏 |
 3 メジロの嘴: 黄色い花粉が嘴とその周囲にもついている。画像:©高久晴子氏 |
| 花蜜食の鳥としての特長: 【軽体重】 体重が10g程と軽いので、ツバキの花びらに足をかけて蜜を吸うことができる。 【舌】 熱帯の花蜜食の鳥、ハチドリ類・タイヨウチョウ類などと同じ構造。 ★サイト「平塚市立博物館」「野鳥の観察④」 |
 4 ホバリングするヒヨドリ: 写画像:©高久晴子氏 |
 5 メジロの舌:「平塚市立博物館」のサイトでは舌の構造図があった。画像:©高久晴子氏 |
| 2: 鳥媒花 |
・ 【初冬~冬】サザンカ、キダチアロエ、ビワ(11月~) ・ 【冬~早春】ウメ(2月中旬~下旬)、ヤブツバキ(2月下旬~3月) ・ 【早 春】サクラ類(カワズザクラは2月下旬頃から咲くき、ソメイヨシノは3月下旬頃から咲く |
 1. サザンカ:借用画像・©高久晴子氏 |
 2. キダチアロエ:撮影:2014/12/30 |
 3. ビワ:撮影:2014/11/24: (生態系被害防止外来種、産業管理外来種-178) |
 4. ウメ:基部の橙色の一部が光るのが蜜の結晶か?撮影2015/03/15 |
 5. ヤブツバキ(左字をクリックすると本HP俳句へジャンプ):花びらの黒い点はメジロが足をかけた痕。撮影:09/03/18 |
 6. ソメイヨシノ: 借用画像:©鳥川 豊氏 |
| 3: 鳥媒花: ウメ |
★本サイト「ウメ」参照。 |
 1. メジロとウメ:借用画像・©高久晴子氏 |
 2. メジロとウメ借用画像・©高久晴子氏 |
 3. ヒヨドリとウメ:借用画像・©高久晴子氏 |
 ヒヨドリとウメ:杉並区北西部で撮影:2015/03/08 |
 ヒヨドリとウメ:左写真と同日同所 |
 ヒヨドリとウメ:曇りだった:区外で撮影:2015/03/10 |
| 4: 鳥媒花: サクラ類 |
★本サイト「ソメイヨシノ」参照。 |
 1. メジロとサクラ:借用画像・©高久晴子氏 |
 2. ヒヨドリとサクラ(1):借用画像・©高久晴子氏 |
 3. ヒヨドリとサクラ(2):借用画像・©高久晴子氏 |
| 受粉に貢献せず、サクラの花を千切って蜜を吸う鳥たち(スズメ、ヤマガラ、シジュウカラ)。 ヤマガラとシジュウカラが花を千切って盗蜜する情報は高久氏の貴重な観察によるもの | ||
 4. スズメとサクラ: 借用画像・:©高久晴子氏 |
 5. ヤマガラとカンヒザクラ:借用画像・:©高久晴子氏 |
 6. シジュウカラとカンヒザクラ:借用画像・©高久晴子氏 |
| サクラの花(陽光)で盗蜜するワカケホンセイインコ: updated: 2017/04/15 (生態系被害防止外来種、その他の総合対策外来種:13.) |
||
「連絡先 (公財)日本鳥類保護連盟 調査研究室 担当:松永氏、Tel: 03-5378-5691 E-mail: research☆jspb.org(☆を@に変えて送信してください)」。出展:©2014 公益財団法人 日本鳥類保護連盟、ホームページ。(閲覧:2017/04/15)。ここで掲載した情報はすでにお知らせしました。(2017/03下旬) |
| 2017年、サクラ(陽光)でワカケホンセイインコが盗蜜:撮影:杉並区北西部、2017/03/27、29、31。 | ||
 |
 |
 |
| 1) 陽光はソメイヨシノより先に咲き、この日は、ほぼ満開状態です。 | 2)雄のワカケホンセイインコが二羽来て盗蜜していました。 | 3)左写真の拡大。 |
 |
 |
 |
| 4) 蜜を吸っているようです。 | 5)花はなく蕾だけに。 | 6)樹下はピンクの絨毯になりました。 |
 |
 |
 |
| 7)落花の萼筒にはこんな穴が。 | 8)ついに別の株に移動して、2羽がすごい勢いで花をちぎり始めました。 | 9)3/31は雨にもかかわらず、来ていました。 |
| 2016年、サクラ(陽光)でワカケホンセイインコが盗蜜していました:撮影:杉並区北西部 | ||
 1)撮影:2016/03/25 |
 2)撮影:2016/03/25 |
 3)武蔵野市で撮影:2016/03/28・©安藤伸良氏・借用画像 |
| 上段の陽光(サクラの仲間)にヒヨドリが吸蜜に飛来。 杉並区北西部:2016/03/26 | ||
 4)ヒヨドリ(1) |
 5)ヒヨドリ(2) |
 6)陽光の花 |
| 2015年、サクラ(陽光)の花で盗蜜するワカケホンセイインコ、撮影:杉並区北西部。掲載:2015/03/28) | ||
 1)雄:とまり枝にしているサクラの花を見ていただきたい。坊主状態は誰の仕業?撮影:2015/03/27 |
 2)雌: 次の日にも何回か見に行ったが、夕方にようやくいました。撮影:2015/03/28 |
 3)左の鳥の次の瞬間、少し下を向いて、次には花を落した。どうも切り口から蜜を吸っているようだ。 |
 4)嘴はサクラ色でした。 撮影:2015/03/30 |
 5)こんなこともします。 撮影:2015/03/30 |
 6)こちらの木には2羽。 撮影:2015/03/30 |
 7)切取られたサクラの花(1):かなりの速度で萼頭の基部を霰のように切り落とすので、ワカケホンセイインコが来ているのが分かるほど。 |
 8)切取られたサクラの花(2) 見ていると、花を嘴でくわえて数秒で落している。瞬時に蜜を吸っているようだ。花は「陽光」とのこと。 |
 9)切取られたサクラの花(3) 9)切取られたサクラの花(3)左写真を拡大。撮影:2015/03/28 |
| 5: 鳥媒花: ビワ: (生態系被害防止外来種、産業管理外来種-178) |
東京で11月下旬に強い芳香に誘われて上をむくと、ビワの花が咲いていた。鳥媒花には赤いもの、匂いがないものが多いとのことだが、ビワやウメは白花(紅梅もあるが)で、芳香があるのはなぜだろう?白花だから? ・ビワはたくさんの花を集めて、大きく見せている。ウメは葉の展開前なので、多数咲く花は鳥からも見えるのだろうか?また、芳香は鳥も感じることができるのだろうか? 2)ハチやアブ(『したたかな植物たち』P171、多田多恵子)、3)メジロとヒヨドリ(下段写真)。 ★本サイト「ビワ」参照。 |
 1)メジロとビワの花: 2013/03月・借用画像・©高久晴子氏 |
 2)メジロとビワの花:杉並区北西部・2014/12/30 |
 3)ヒヨドリとビワ:杉並区北西部・2014/11/29 3)ヒヨドリとビワ:杉並区北西部・2014/11/29 |
| 6: 鳥媒花: ヤブツバキ |
★本HP「ヤブツバキ と 本HP俳句(2021の1花椿)青字をクリックするとジャンプします。 |
 1)メジロとヤブツバキ:メジロは体重が軽いので、花びらに足をかけて蜜を吸っている。借用画像・©田中 肇氏 |
 2)ヤブツバキ:花びらの黒い点はメジロが足をかけた痕。撮影:09/03/18 |
 3)ヒヨドリとヤブツバキ:ヒヨドリは重いので、枝から身を乗り出して蜜を吸っている。借用画像・©田中 肇氏 |
 4)メジロとツバキの花:借用画像・©笹本恵子氏 |
 5)メジロが花びらに足をかけた跡:杉並区北西部で撮影 |
 6)メジロとツバキ:借用画像・©高久晴子氏 |
| 7: 鳥に散布される種子(タネ):「種子分散共生系」 |
植物は固着性ゆえ、基本的に自ら動くことができない、しかし、果実が成熟したとき親元から離れ、子孫を新天地へ運ぶ機会がある。その一つが動物(ここでは鳥に特化しているの「鳥被食散布」)に果実を運ばせる「動物被食散布」の方法。 1)親から離れる(光、生存競争、食害・病害などの問題があるので)、 2)広範囲に分散させる(生存選択肢の向上のため)、 3)適切なセーフサイトへ到着させる。そこで、植物は次のように鳥にアピールしている。 1)熟すと外皮を黒や赤などの目立つ色にする(熟期教る)、 2)動物に運んでもらうための報酬として可食部を用意している、 3)種子は不消化で、別の場所でフンと共に散布してもらう。だから種子は硬い殻で保護されている。 果実を食べた鳥は「果肉の栄養を摂取するこっとになるし、植物の方は種子を運んでもらうことになる。したがって、おたがいにプラスになり、いわば相利共生の関係にあたると考えられる」。 「被食鳥散布の通常の散布距離は数100mぐらいで、1000m以上運ばれることは少ない」。「冬期にツグミやヒヨドリは周辺地域の中で最も樹高の高い樹木、たとえばメタセコイアによくあつまり、その木の下においたトラップに最高一日に1㎡あたり1000個以上の種子が鳥のフンとともに落下した」。 *1『絵でわかる生態系のしくみ』P84-85、鷲谷いづみ、㈱講談社 *2『木と動物の森づくり』P116、斎藤新一郎、2008、㈱八坂書房 *3『種子はひろがる』P97、中西弘樹、1994㈱平凡社 |
 1)植物は固着性 *1P85を参考にPPで作成 |
 2)果実に色をつけ、果肉をつけて鳥に運んでもらう。借用画像・© 高久晴子氏 |
 なぜ 3)親は子を新天地へ送り出すの?*1P85を参考にPPで作成 |
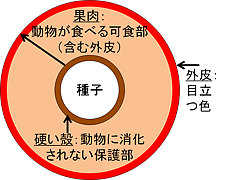 4)果実のイメージ:★サイト「福原のページ」を参考にPPで作成 |
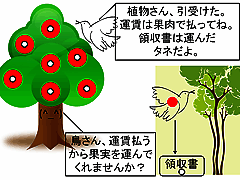 5)植物と鳥:種子(タネ)分散共生 *2:P115を参考にPPで作成 |
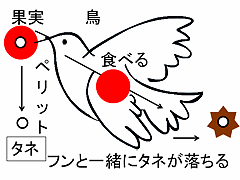 6)果実・鳥・タネ *2:P115を参考にPPで作成 |
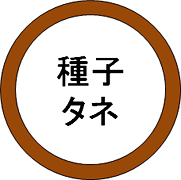 7)鳥のお腹で消化されないよう種子(タネ)を硬い殻で保護している |
 8)ベリー類のタネが見られるフン: 高尾山稜で撮影・2014/06/04 |
 9)ナンテンを食べに来たヒヨドリが残したフン。杉並区北西部で撮影:2015/02/20 |
| 8: 果実の分類(広葉樹):他に明記なき場合、杉並区で筆者撮影、 杉並区外で撮影した植物も杉並区にあるものに限り掲載。 |
|||
| 分類 | 果実のつくり(下段写真では乾果はさく果以外掲載していない) 種名(下段写真掲載した植物名を入れた):黒い果実:含青、紫。 赤い果実:含黄 |
||
| 乾 果 |
裂果 2/5 |
豆果、 さく果と袋果: 左両果実には多肉質の仮種子の場合がある: 黒1)アカメガシワ、黒5)ゴンズイ、 赤8)コブシ、赤11)ツリバナ、赤12)ツルウメモドキ、赤13)トベラ、赤19)マユミ |
|
| 不裂果 | 翼果、分離翼果、そう果、えい果、堅果 | ||
| 分類 | 果実のつくり | 種名(下段写真掲載した植物名を入れた): 黒い果実:含青、紫。 赤い果実:含黄 |
|
| 多肉果 | 単果 | 核果: 7/5 | 黒い果実: 黒3)クサギ、黒6)サワフタギ、7黒)トウネズミモチ、 黒10)ミズキ)、黒11)ムクノキ、黒12)ムラサキシキブ、黒14)ユズリハ、 赤い果実: 赤3)エノキ、赤5)ガマズミ、赤14)ニワトコ、赤20)マンリョウ、 21)ヤマモモ |
| 液果:3//7 | 黒い果実: 黒4)クスノキ、黒9)ヒサカキ、12黒)ヤブラン 赤い果実: 赤1)イイギリ、赤2)ウグイスカグラ、6)カラスウリ、 赤9)サネカズラ、赤10)シロダモ、赤17-18)マメガキ |
||
| ミカン果:1 | 赤7)カラタチ | ||
| ナシ(状)果:1/1 | 黒8)シャリンバイ、赤16)ピラカンサ | ||
| 複果 | バラ(状)果:1 | 赤15)ノイバラ | |
| キイチゴ(状)果:1 | 赤4)エビガライチゴ | ||
| イチジク(状)果:1 | 黒2)イヌビワ | ||
| クワ(状)果:1 | 黒13)ヤマグワ(手持写真に黒熟がなかったので替わりにマグワを掲載) | ||
| 9: 発芽植物:緑地などで発芽してくる植物(鳥散布以外に根萌芽する植物も含む) | ||
| 高木(含亜高木) | 低木 | 林床植物(含つる性植物) |
 |
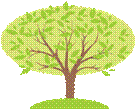 |
 |
| 1) アカメガシワ、イイギリ、エノキ、クサギ、クスノキ、コブシ、ゴンズイ、 |
2)アオキ、イヌビワ、イボタノキ、ウグイスカグラ、ガマズミ、カラタチ、サワフタギ、シャリンバイ、センリョウ、ツリバナ、ナンテン、ニワトコ、ヒサカキ、ピラカンサ、マユミ、 |
3)アマチャズル、イチゴ類、エビガライチゴ(含他キイチゴ類)、オモト、カラスウリ、キカラウスリ、キチジョウソウ、サネカズラ、スイカズラ、センリョウ、ツルウメモドキ、ノイバラ、ヒヨドリジョウゴ、マンリョウ、ヤブラン、 |
| 10: 黒い果実: (含む青、紫)あいうえお順に掲載 ★本サイトに植物の詳細ページあり。 |
||
 1)アカメガシワ:高木:さく果 |
 2)イヌビワ:低木: イチジク状果:雌果のう |
 3)クサギ:高木:核果:「2色効果」で鳥にアピール。 |
 4)クスノキ:高木:液果 |
 5)ゴンズイ:高木:袋果:「2色効果」で鳥にアピール。 |
 6)サワフタギ:低木:核果:借用画像・©福原達人氏 |
 7)トウネズミモチ:高木:核果:(生態系被害防止外来種、重点対策外来種-53) |
 8)シャリンバイ:低木:ナシ状果 |
 9)ヒサカキ:低木:液果 |
 10)ミズキ:高木:核果:ムクドリが群れで食べに来る |
 11)ムクノキ:高木:核果:借用画像・須永三紀夫氏 |
 12)ムラサキシキブ:低木:核果 |
 13)マグワ:高木:クワ状果:背景に赤い果実もまじる。これも2色効果らしい。 |
 14)ユズリハ:高木:核果 果実が大きく、鳥に人気がある |
 15)ヤブラン:林床草本:液果状: 食べているのは弱警戒心のキジバト? |
| 11: 赤い果実 (含む黄色)あいうえお順に掲載 ★本サイトに植物の詳細ページあり。 |
||
 1)イイギリとヒヨドリ:高木:液果:撮影:石神井公園 1)イイギリとヒヨドリ:高木:液果:撮影:石神井公園 |
 2)ウグイスカグラ:低木:液果:熟期は初夏のせいか、直ぐなくなる |
 3)エノキ:高木:核果:落ちた果実をカモ類、キジバトが食べている |
 4)エビガライチゴ:つる性:キイチゴ状果:熟期は初夏 |
 5)ガマズミ:低木:核果 |
 6)カラスウリ:つる性:液果 |
 7)カラタチ:低木:ミカン状果 |
 8)コブシ:高木:袋果:落下したもの |
 9)サネカズラ:蔓性:液果 |
 10)シロダモ:高木:液果 |
 11)ツリバナ:低木:さく果 |
 12)ツルウメモドキとメジロ:つる性:さく果。借用画像・©高久晴子氏 |
 13)トベラ:高木:さく果:浜離宮で |
 14)ニワトコ:低木:核果:熟期初夏 |
 15)ノイバラ:つる性:バラ状果 |
 16)ピラカンサとメジロ:高木:ナシ状果。借用画像・©高久晴子氏:(生態系被害防止外来種、その他の総合対策外来種-119) |
 17)マメガキとメジロ:高木:液果:借用画像・:©高久晴子氏 |
 18)マメガキとヒヨドリ:高木:液果。借用画像・©高久晴子氏 |
 19)マユミ:低木:さく果 |
 20)マンリョウ:小低木:核果 |
 21)ヤマモモ:高木:核果:熟期初夏 |
